記憶力のメカニズム‐1

記憶力!自信がありますか?
記憶力というとかなり年配者なのに抜群にいい人、若いのに大丈夫?な人など、いろいろあります
「暗記力がいいのは20歳前まででしょ?」と言われていますが、子供の得意なのは『無意味暗記』で「とにかく覚えなさい!」と意味が分からなくても記憶できるのです
これは10代が強いですが、大人は『意味暗記』ならば記憶できますが、無意味暗記は苦痛になっていきます
一概に「年をとると記憶力は落ちる」とは言い切れません
忘れたい記憶もありますが、ビジネスの世界、学習の世界、人の育成の世界ではやはり記憶力は重要な能力です
以前、企業の教育担当者の講習会で 記憶力UPの為には『ポリフェノールと おとといのことを思い出す習慣』と習いましたが、記憶力は訓練でかなり改善できます
毎日の夕食時「おとといの夕食は何食べたか?」と思い出す癖をつけるだけで記憶力は良くなるようです
この記憶力をテーマを数回に分けて進めていきます
心理学からまずは「記憶のメカニズム」を解説していきたいと思います
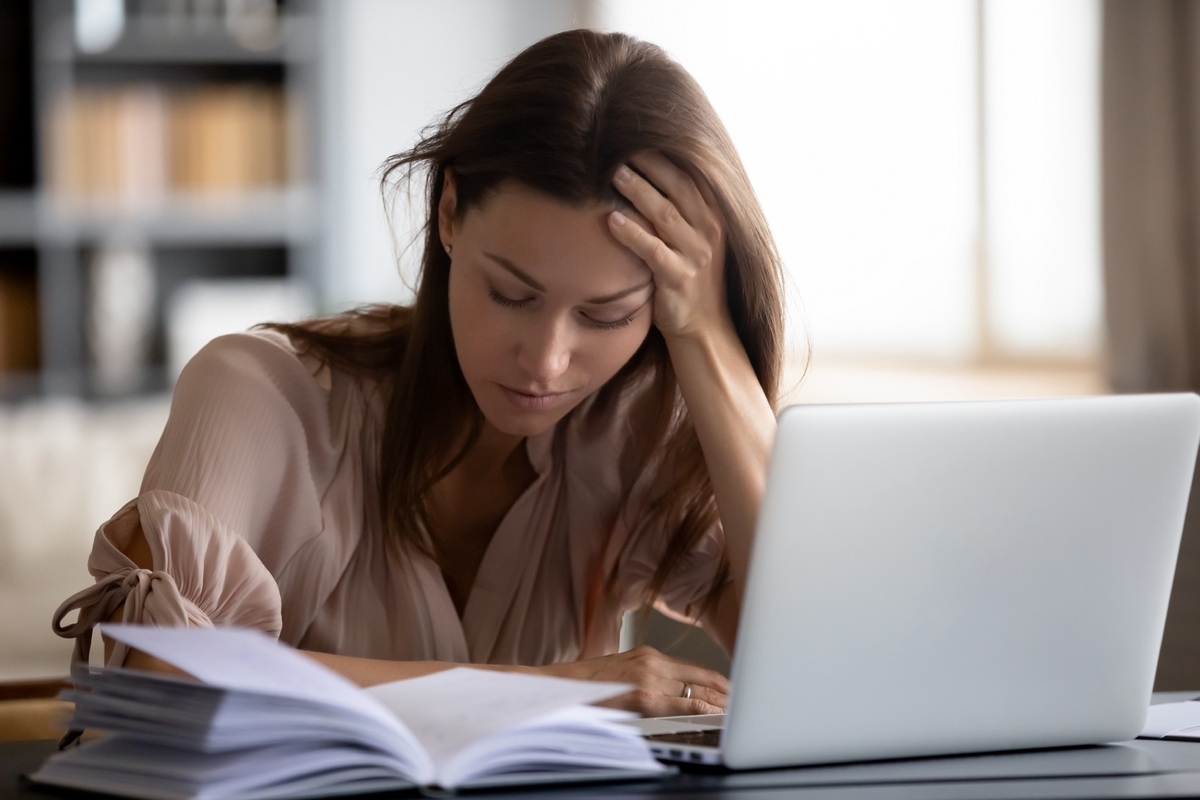
記憶の第一段階
まずは記憶のシステムを理解します
記憶は
①記銘(きめい)=コード化
②保持=保存
③再生=検索
から成り立っています
記銘=コード化について説明しますと、われわれは外界から多くの刺激を受けていますが、この刺激から受けた情報は神経系や感覚器官によって処理され、あるものは記憶に残り、あるものは消去されてしまします
この記憶の段階の一番最初が『記銘』という段階です
記銘の段階は、刺激からえられた情報の重要度、好感度により変化します
たとえば、いやいや覚えさせられてるものと、楽しみながら学んでいるものとでは記銘に違いが出ます
記銘は記憶の第一段階なので、非常に重要なプロセスと言えます

記憶のメカニズムの第2段階
『記銘=コード化』の過程が成功すると、次はその情報を忘れないように頭に留めておく『保持=保存』の段階になります
勉強でもビジネスの世界でも、記憶しようとメモをとったり、復唱したりしてなんとか 頭に情報を刻み込もうとしますよね
努力して頭の残そうと努める状態が保持の過程で、努力なしに記憶は出来ませんので 私たちは繰り返して記憶の定着を図る『リハーサル』を行います
実験によるとリハーサルを行うことによりすぐに忘れてしまう=短期記憶から、長期間記憶が定着する=長期記憶へ情報が移りやすいようです
この『保持』の段階では《努力》が記憶の定着時間を左右します
勉強でも、ビジネスでも覚えるべきことを頭に記憶させるには、とにかく繰り返し刻み込もうとする努力が重要と言うことです
子供の入試試験でも、国語、算数(数学)、理科、社会、英語などが重要視されるのは、才能より努力が占める割合が大きいからであり、 美術、音楽、体育などは才能が占める割合が多いといえます
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました







