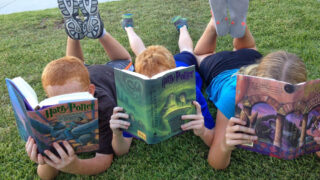青少年期の発達

青少年期の発達=同一性の確立
青少年期の発達の特徴に移ります
ここでの発達は児童・学童期ほど深い深層心理には入り込みませんが、成人後の性格に大きな影響を与えます
青少年期は自我も芽生え、子供と大人の中間に位置する子供ではないが大人でもないという不安定な時期です
「自分はどんな人生を歩むのか?」
「どんな才能があるのか?」
「自分はどんな人間なのか?」
「自分はなにができるのか?」
などの深い疑問を抱え、試行錯誤しながら答えを見つけていかなければならない時期です
考え方も未完成、感情の起伏も激しく孤独も求めるし集団も求めます
この不安定な青少年期の発達課題は『自分を独立したひとりの人間として認識すること=同一性の確立』です
この時期から「心の不安を取り除きたい」「自分をよく知りたい」「相手をもっとよく理解したい」などの欲求が強くなり、心理学や占いなどに興味を持ち始めます
独立心と依存心が両方向に存在しており、なかなか複雑な時期でもあります
どの社員もカウンセリングをしていると、この青少年期の自分のことはよく語ります
精神的に自分の足で歩き始めた時期だからでしょう

青少年期=独立期
幼児期が家族=親との安定した関係が重要であったように、青少年期は家族以外の人間関係に安定した自分の居場所を確立していくことが重要になります
青少年期のキーワードは『自我の独立』で、経済的には独立できなくても一人の人間として、親から精神的に独立しようとするときです
従って、頭を押さえようとすると当然反発してきます
親もまだまだ未熟な子供に対して注意・指導しますので、ここで反抗期というものが生まれ、 この時期の反抗期とは極めて自然な親子の現象なのです
仲間や社会との関わりを通じて、集団の中で自分を独立した人間として適応させるための方法を身に付けなければならない非常に重要な時期なのです
この時期は自己が混乱してしまい、自分が社会のどこに位置づけられたのかを見失ってしまう『自我同一拡散』の状態に陥ることもあります
この拡散を乗り切り、自分の進むべき道と居場所を見つけ、自分を一人の人間としての存在価値を見出すことが非常に重要な課題なのです
またこの時期は本人も、親も『進学=受験=学力』に目が行きがちで、健康・学力以上にこの青少年期特有の社交性を親も考えるべきでしょう
友人関係の安定は精神的な安定に直結しますので、この時期の人間関係の不安定は引きこもりなどの現状も生みますが、そうまでならずとも社会人になってからも深層心理に傷として刻まれ、社交性・和合性に影響を与えます
青少年期は自分の子供の和合性、友達関係の築き方をよく観察すべきです

成人前の発達について考える
子供の発達にはその時期に合わせた課題があり、それぞれの発達課題をクリアして、社会生活に柔軟に溶け込み、安定した居場所を見つけることが『精神安定』『正常な社会参加』につながります
親は学業の成績・学校や健康面への配慮に加え、この発達に合わせた『環境作り』に目を向けることが大切です
臨界期という言葉がありますが、生まれたばかりの猫の子に目隠しを2カ月するとその猫は一生目が見えなくなります
この2か月間が、正常な光の刺激を受け、目が発達をする猫の視力の臨界期ということです
子供にもそれぞれ人間社会で生きていくために身に付けるべき課題の臨界期があります
発達課題が環境的にうまく達成できないと社会不適合な部分が出来ます
また東洋人間学を代表する算命学でも『バランス=中庸』を最良としますので「 発達が早すぎてもいけない」ということです
『早く咲く花は散るのも早い』ということも頭に入れておいてください
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました